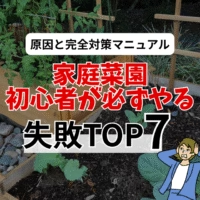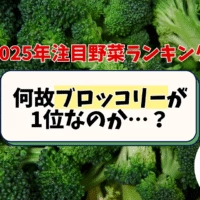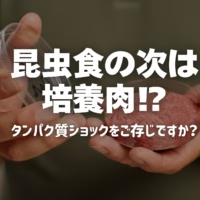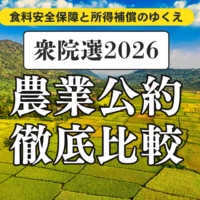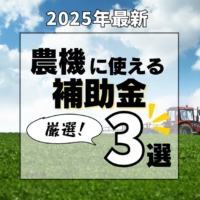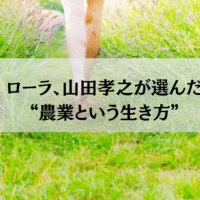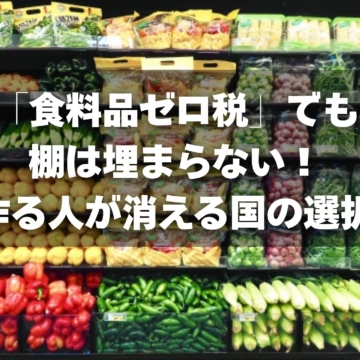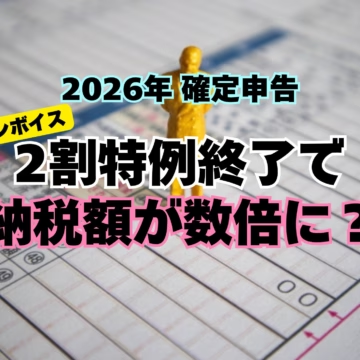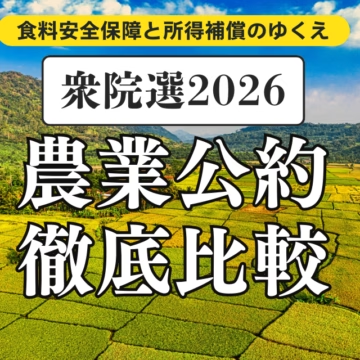令和時代の農業はこう変わる:農水省「新・基本計画」と最新政策の全貌
1. 政策転換の背景:改正基本法と「基本計画2025」の成立
2025年、日本の農業政策は歴史的な転換期を迎えました。その基盤となるのが、2024年に改正された
「食料・農業・農村基本法」です。この改正は、前回の改正から25年ぶりとなる大改正であり、「食料安全保障の強化」を最上位概念として位置づけた点が最大の特徴です。
これを受け、農林水産省は、新たな指針として「食料・農業・農村基本計画(基本計画2025)」を閣議決定しました。この基本計画2025は、令和時代の農業改革を象徴するものであり、単に食料の供給量を確保するだけでなく、危機に強い農業構造の構築を目指しています。
この転換の背景には、主に三つの深刻な課題があります。
1. 地政学リスクの増大とサプライチェーンの脆弱化
ロシアによるウクライナ侵攻や国際的な貿易摩擦の激化により、小麦や飼料穀物といった輸入依存度の高い主要品目の価格が高騰し、供給途絶のリスクが顕在化しました。
2. 担い手の高齢化と農地の非効率な利用
農業従事者の減少と高齢化が加速し、耕作放棄地の増加や、農地が細分化されたまま残る非効率な農業構造が生産性を阻害していました。
3. 気候変動と災害の激甚化
頻発する異常気象や大規模災害から、農業生産基盤を守り、安定的な生産を継続するための強靭化が喫緊の課題となっています。
基本計画2025は、これらの課題に対応するため、「食料安全保障」「スマート農業の推進」「農地集約と担い手育成」「インフラの強靭化」の四つの柱で構成され、日本の農業を安全保障と持続可能性を担う基盤産業へと進化させることを目指しています。
2. 「食料安全保障」を核とした戦略的施策
基本計画2025の最優先課題は、食料安全保障の確立です。特に、輸入依存度の高い小麦、大豆、飼料作物などの国産化を強く推進し、有事の際にも国民生活を支える「食料自給力の維持・向上」が目標とされました。
2.1. 水田活用の戦略的転換と高収益化
コメの需要減少が続く中で、農水省は「水田活用の直接支払交付金」を戦略的に活用し、水田を単なるコメ生産の場から、多様な高収益作物の生産拠点へと転換させる施策を強化しています。
転作推進の強化
飼料米やWCS(稲発酵粗飼料)のほか、小麦、大豆、野菜といった戦略的作物への転作を促すため、交付金の単価設定や対象基準が見直されました。
米粉利用の拡大支援
食料安全保障の観点から、米粉利用の増加は小麦依存度を下げる重要な手段です。米粉用米の生産支援に加え、米粉を活用した新市場向け商品開発や、製粉設備・加工設備の導入への支援が盛り込まれ、川上から川下までの一貫したサプライチェーン構築を後押しします。
2.2. 国産原料の供給力強化と食品産業との連携
小麦・大豆の国産化は、単に生産量を増やすだけでなく、加工・流通体制の整備と一体で進められます。食品メーカーや商社などの食品産業と農業者との連携を強化し、契約栽培の拡大や、国産原料に最適化された加工ラインの構築を支援します。これにより、輸入原料と競合できるコスト競争力と安定供給体制の確立を目指します。
3. 生産性向上と構造改革:農地・技術・インフラの三位一体改革
食料安全保障を実効性のあるものとするためには、農業の構造的な生産性の低さを解消し、国際競争力を持つ効率的な生産体制を築く必要があります。
3.1. 農地集約と農地バンク(農地中間管理機構)の役割強化
日本の農業が抱える最大の課題の一つが農地の細分化と担い手不足です。これを克服するため、地域計画の策定が義務化され、地域ごとに「将来の農地利用の姿」と「誰が、どの農地を担うのか」を明確にすることが求められます。
地域計画の推進
市町村が主導し、地域住民や農業者と話し合い、農地の集積・集約化、遊休農地の解消、経営規模の拡大など、具体的な目標と道筋を定めます。
農地バンクの活用拡大
農地中間管理機構(農地バンク)の機能が強化されます。農地バンクは、離農者などから農地を借り受け、まとまった形で意欲ある担い手(認定農業者、認定新規就農者など)に貸し付けることで、農地の集約化を加速させる中心的な役割を担います。これにより、農業者の経営規模拡大や、新規参入の障壁引き下げが期待されます。
3.2. スマート農業・省力化投資促進プランの拡充
深刻化する人手不足への対応と生産コストの削減のため、スマート農業技術の社会実装が最優先されます。
補助金制度の刷新
自動運転トラクター、ドローンによる農薬散布・生育診断、IoTセンサーによる水管理・環境制御システムなどの導入に対する補助金制度が拡充されました。特に、研究段階の技術だけでなく、現場での実用化レベルに達した技術の導入を強力に後押しする方向性が示されています。
データ駆動型農業の推進
収量、労働時間、投入資材コストなどのデータを統合的に管理し、AIなどが活用しやすい「データ駆動型農業」への転換を支援。これにより、農業経営の「見える化」と「最適化」を進め、生産性向上を目指します。
\\スマート農業おすすめの書籍//
スマート農業を始めるならこの最強の2冊!
「スマート農業」を基礎から実践まで完璧にマスターしたいなら、この2冊が鉄板です。どちらもスマート農業の第一人者である三輪泰史氏の著作。「儲かる農業」を実現するためのノウハウが凝縮されています!
3.3. 土地改良長期計画と農業インフラの強靭化
2025年9月に閣議決定された「土地改良長期計画(令和7〜11年度)」は、農業インフラの維持管理と近代化を両輪で進める計画です。
老朽化施設の更新と災害対策
農業水利施設(ダム、ため池、水路)の老朽化対策と長寿命化が最重点化されました。また、近年頻発する豪雨や地震に備え、農業用インフラの耐災害性強化が進められ、災害時における食料供給途絶のリスクを軽減します。
大区画化・汎用化の推進
複雑で非効率な形状の農地を大規模な区画に整備し直し、水田・畑作間の転換が容易な汎用性の高い農地に改良します。これは、スマート農業機械の導入を容易にし、前述の転作推進とも深く連動する施策です。特に中山間地域においては、ため池の統廃合やパイプライン化などにより、省力化と水利の安定化が進められます。
4. 農業経営者に求められる戦略的行動
農水省の新政策は、農業経営者にとって大きなチャンスを提供するものですが、同時に、従来の慣行農業からの脱却を強く促すものです。この変革期を乗りこなすために、農業経営者は以下の戦略的行動が求められます。
4.1. 政策・地域計画への積極的な関与
最も重要な行動は、地域計画の策定プロセスに積極的に参画することです。
地域との連携強化
自身の農地の利用意向を明確にし、市町村や農地中間管理機構と連携を取りながら、農地集約や遊休農地活用の仕組みに自らの農地を組み込む必要があります。これは、「誰が地域農業を担うのか」という問いに対し、自らが主体的な役割を果たす意思を示すことに他なりません。
補助金・融資情報の収集と活用
スマート農業、高収益作物への転換、施設園芸の高度化など、自身の経営戦略に合致する補助金制度や低利融資(例えば、スーパーL資金、農業近代化資金など)の情報を絶えず更新し、投資計画に組み込むことが必須です。
4.2. データ駆動型経営への転換とKPI思考
国が推奨する「数値で示す農業経営」と整合するため、経営のデータ化を徹底する必要があります。
投資の優先順位付けと費用対効果の明確化
補助金頼みではなく、水管理の自動化、ハウスの環境制御、病害虫対策など、費用対効果(ROI)が高い設備投資から優先的に取り組みます。補助金申請や金融機関への融資申請時には、予測されるコスト削減額や増収額を客観的なデータに基づいて示せるように準備します。
KPI(重要業績評価指標)による管理
収量(反収)、労働時間(時間当たり所得)、燃料・資材コスト(売上高比)、農地集積率などのKPIを設定し、PDCAサイクルを回すことで、経営改善を継続的に行います。
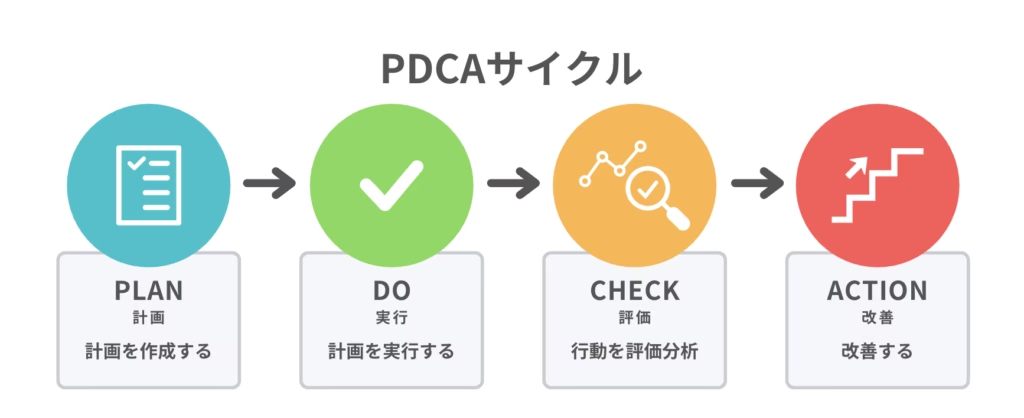
4.3. 経営リスクの多角化と複合化
政策や市場は常に変動するため、一つの収益源や単一の補助金制度に依存する経営は高いリスクを伴います。
作目の複合化と販路の多様化
コメ単作から、政策支援のある小麦・大豆、あるいは高単価の園芸作物などを組み合わせた複合経営へ移行します。また、市場出荷だけでなく、インターネット販売、農産物加工、契約栽培など、複数の販路を組み合わせることで、価格変動リスクを低減します。
災害対策と保険の活用
施設の強靭化と並行して、収入保険や農業共済制度などを積極的に活用し、気象リスクや市場リスクに対する経営のセーフティネットを構築します。
⚠️ 政策の活用に関する注意点
ここに記載する政策や計画は、2025年時点の公表情報に基づく解説であり、あくまで一例の紹介です。農業政策は、国際情勢や財政状況により数年ごとに見直されることが常であり、補助金制度の内容や適用要件は年度や地域によって変動する可能性があります。実際に政策を活用される際は、必ず農林水産省の公式文書、地方自治体の情報、および関連団体の最新のガイダンスをご確認ください。
まとめ:未来志向の「戦略的農業」へ
令和時代の日本の農業は、国際情勢に左右されない食料安全保障の確立を大前提とし、その実現のためにスマート技術の導入と農地集約による構造改革を断行するフェーズに入りました。農水省の「新・基本計画2025」と関連施策は、この改革の全体像を示しています。
これらの政策は、従来の農業を守るための「保護政策」から、未来の食料供給を担うための「投資・戦略政策」へとその性質を変えつつあります。農業経営者には、制度を単に受け身で利用するだけでなく、政策・市場・環境の3要素を同時に読み解き、自らの経営を未来志向で設計し直す戦略的かつ積極的な姿勢が求められます。補助金や支援策を梃子に、自らの農業を国際競争力のある、持続可能な産業へと進化させていくことこそが、令和の農業経営者に課された使命と言えるでしょう。
参考文献
農林水産省:食料・農業・農村基本法(2024年改正)
https://www.maff.go.jp/j/basiclaw/index.html
農林水産省:食料・農業・農村基本計画(基本計画2025)https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-61.pdf
農林水産省:令和7年度農林水産予算 概算決定の概要
https://www.maff.go.jp/j/budget/r7kettei.html
農林水産省:土地改良長期計画(令和7〜11年度)
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/totikai/index.html
農地中間管理機構(農地バンク)関連資料
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html
農畜産業振興機構(alic)関連調査報告
農畜産業振興機構:広報webマガジン「alic」2024年10月号