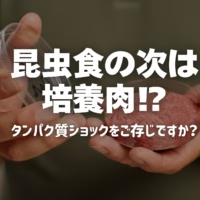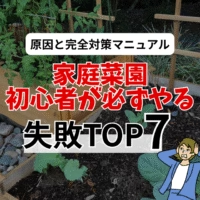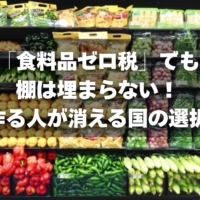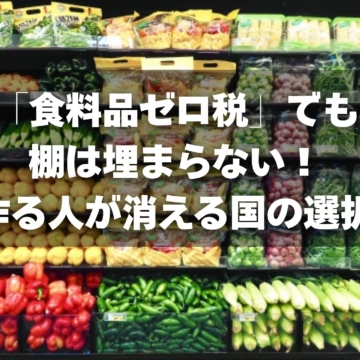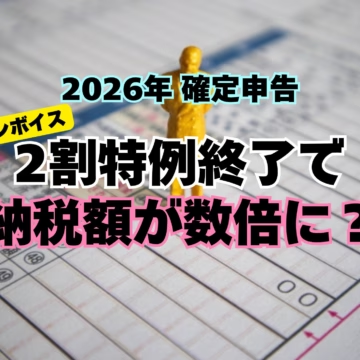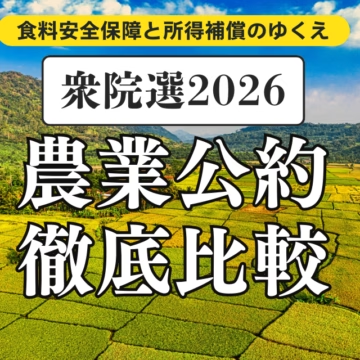【徹底解説】高市早苗氏の農業政策|食料自給率「100%」構想と「稼げる農業」3つの柱
2026年1月8日更新
はじめに:なぜ今、高市早苗氏の農業政策が注目されるのか
私たちの食卓に並ぶ食料の約6割が海外からの輸入に頼っているという事実をご存知でしょうか。日本の食料自給率はカロリーベースでわずか38%(令和5年度)。近年の世界的な物価高騰や不安定な国際情勢は、私たちの生活に直接影響を与えています。
この状況は、食料供給が国家の存立基盤そのものを揺るがしかねないという、経済安全保障上の根本的な脆弱性を示しています。
本記事では、経済安全保障担当大臣などを歴任した高市早苗氏が提唱する農業政策に焦点を当てます。彼女の政策は単なる産業振興策ではなく、食料問題を国家戦略の中核に据えるものです。
「食料自給率を限りなく100%に近づける」という野心的な目標と、「稼げる農業」への転換というビジョンについて、その背景から具体的な施策まで、SEOの視点も交えて徹底的に解説します。

1. 日本の「食」が直面する5つの深刻な課題
高市氏の農業政策を理解する上で、まず日本の農業が抱える構造的な課題を整理する必要があります。
- 低い食料自給率: 38%という水準は主要先進国でも極めて低く、有事の際の国民の生命維持に直結するリスクです。
- 生産者の高齢化と後継者不足: 農業従事者の減少は、国内の生産基盤そのものを揺るがし、耕作放棄地の増加を招いています。
- 生産コストの歴史的高騰: 肥料、飼料、燃料価格の高騰が、多くの農業者の経営を圧迫しています。
- サプライチェーンの脆弱性: 肥料原料の多くを特定の国(中国など)に依存している現状は、経済安全保障上の大きな弱点です。
- 国民の認識ギャップ: MS&ADインターリスク総研の調査(2024年)では、食料安全保障への不安を感じる人が6割を超える一方、言葉の認知度は2割未満という結果が出ています。
2. 高市氏が掲げる農業の未来像:「稼げる農業」への転換
高市氏は、従来の「守りの農政」から脱却し、以下の2つのビジョンを掲げています。
① 「稼げる農業」への構造改革
農業を国の成長産業と位置づけ、収益性を高めるための技術革新(スマート農業等)を推進します。
② 自給率「限りなく100%」への挑戦
「食料安全保障は、国民の命を守るための経済安全保障の要」と捉え、国内生産能力を最大限に引き出すことを目指します。
3. 高市農業政策の「3つの柱」を徹底解剖
高市氏の構想は、日本の国家的なレジリエンス(強靭性)を構築するための、以下の3つの柱で構成されています。
柱① 【緊急支援】現場の「止血」とレジリエンスの強化
「農政は現場が第一」という理念に基づき、喫緊の課題に苦しむ生産者への迅速な支援を重視しています。
- 資材・燃料高騰対策: 燃料価格の暫定税率見直しや、肥料・飼料高騰に対するスピーディーな資金支援。
- 地域密着型支援: 中山間地の維持や鳥獣被害対策など、地域ごとに異なる課題に柔軟に対応できる交付金の拡充。
柱② 【構造改革】「攻めの農政」へのパラダイムシフト
長年続いてきた生産抑制型の農政を終わらせ、生産者の意欲を引き出す改革です。
- 減反政策の抜本的見直し: 「米を作るな」というメッセージから「需要を創出し、生産能力を最大化する」方向へ転換。
- スマート農業の加速: 準天頂衛星(みちびき)を活用した自動走行農機やAIによる生育管理で、大規模化と効率化を推進します。
柱③ 【技術革新】技術主権の確立と「システム」の輸出
日本の農業を、気候変動に左右されない強靭な成長産業へと変革させます。
- 完全閉鎖型植物工場と陸上養殖: 天候に左右されず、災害時の食料供給拠点にもなる次世代技術への投資。
- デュアル輸出戦略: 高品質な「農産物」だけでなく、それを育てる「農業システム」そのものを世界へ輸出。
- 知財・種苗の徹底保護: 日本が開発した優良品種の海外流出を防ぐための厳格な法的措置。
4. 食料は「経済安全保障」の要:肥料問題に見る国家戦略
高市氏が提唱する農業政策の最大の特徴は、「経済安全保障推進法」との連動にあります。
特に「肥料」は、国民の生存に不可欠な特定重要物資に指定されています。リン鉱石や塩化カリウムなどの原料を海外(特に中国)に依存している現状を打破するため、国内での代替原料開発や備蓄支援を強化。これは、農業政策が単なる産業支援ではなく、国家の安全保障そのものであることを意味しています。
5. まとめ:高市氏の描く「強い農業」が日本の未来を拓く
高市早苗氏の農業政策は、「危機対応(緊急支援)」と「成長戦略(構造改革・技術革新)」の二段構えです。
食料を「国力」と再定義し、経済安全保障の基盤に据え直すというこの構想は、日本の農業を「守り」から「戦略的な攻め」へと転換させる可能性を秘めています。実務的な財源確保や現場への浸透といった課題はありますが、国民全体の意識が変わる大きなきっかけとなるでしょう。
\\こちらの記事も合わせ読んでみてください!//
参照・出典一覧
政策情報・一次情報
- 高市早苗 公式政策サイト(自民党総裁選2025)
https://sosaisen-sanae.com/policycontent - 高市早苗 政策演説(YouTube)
高市早苗チャンネル
https://www.youtube.com/@takaichisanaechannel/videos
・【国家の品格】米や食料品などの物価高騰へ国家の支援は?
・【自民党総裁選】政権公約 食料安全保障政策について【食料自給率100%目標】
・【高市早苗に聞く】供給途絶のリスクに備える「特定重要物資」について - 農林水産省公式情報
・食料安全保障とは
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/1.html
・日本農業の現状と課題
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/
・スマート農業推進事業
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/
ニュース・解説記事
- S&ADインターリスク総研株式会社(2025年4月16日).
消費者の食料安全保障に関する意識について~アンケート調査結果より(2024年版).MSコンパス.https://mscompass.ms-ins.com/business-news/food-security-questionary/ (2025年10月16日アクセス) - 内外ニュースチャンネル(2025年4月)
講演要約 高市氏202504 「日本の国力を強くするために」https://www.naigainews.jp/%E6%87%87%E8%AB%87%E4%BC%9A/%E6%87%87%E8%AB%87%E4%BC%9A%E8%AC%9B%E6%BC%94%E8%A6%81%E7%B4%84/%E8%AC%9B%E6%BC%94%E8%A6%81%E7%B4%84-%E9%AB%98%E5%B8%82%E6%B0%8F202504/
(2025年10月16日アクセス) - ポリシーニュース
ポリシーニュース|高市早苗氏インタビュー
https://www.policynews.jp/interview/2025/takaichi.html (2025年10月16日アクセス)



-200x200.avif)