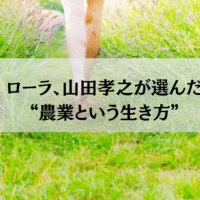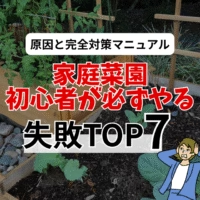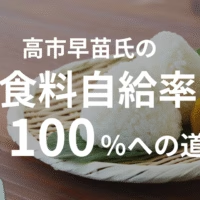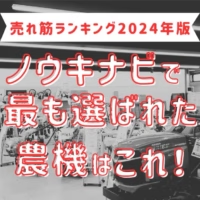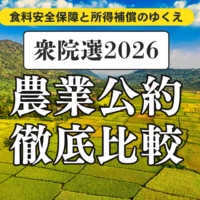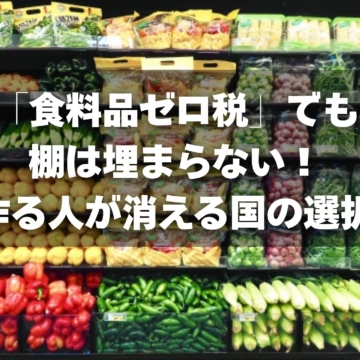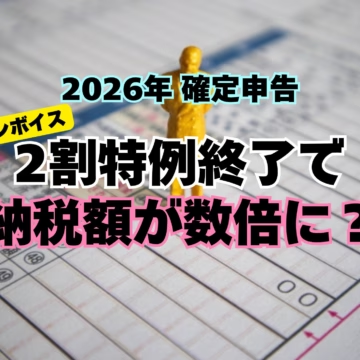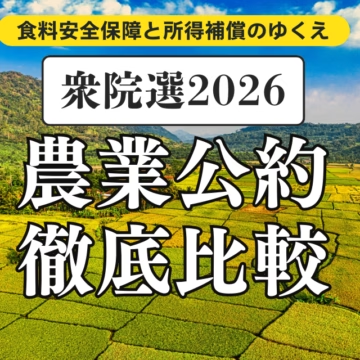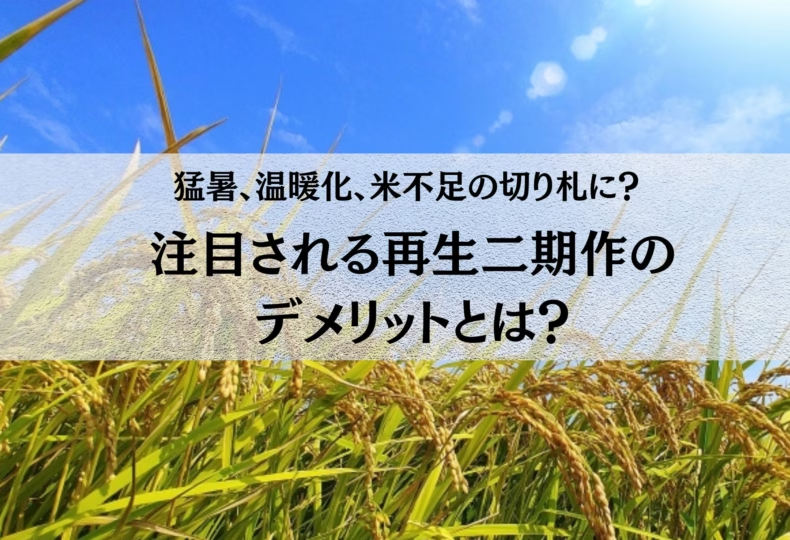
猛暑、温暖化、米不足の切り札に?注目される再生二期作のデメリットとは?
最近、「再生二期作」という言葉をニュースや記事で耳にされた方も多いのではないでしょうか。これは、通常の田植えで育てた稲を1回目に収穫した後、株元から再び芽吹いた「ひこばえ(二番穂)」を育て、再度収穫するという方法です。一度の田植えで済ませられるため、手間やコストを抑えつつ収量を増やす新たな栽培技術として注目を集めています。
とはいえ、すべてが順調というわけではなく、現場からは「期待と不安」が入り混じった声も聞かれます。本記事では、再生二期作の可能性と課題を整理し、今後の展望を一緒に考えてみたいと思います。
■ 温暖化と米不足が後押しする再生二期作
背景には、いくつかの重要な要因が重なっています。
近年、猛暑が長引き、稲の生育期間が延びたことで、再生二期作に適した気候条件が整いつつあります。一方で、国内ではコメ不足が深刻化し、スーパーでも高値が続いています。
さらに2025年7月、政府はアメリカとの関税交渉の中で「ミニマムアクセス米」の輸入割合を拡大する方針を打ち出しました。これにより、国内生産者の間では不安が広がっています。
こうした状況から「国内での増産体制を強化すべき」との声が高まり、再生二期作がその有力な手段として注目されているのです。
■ 実際の取り組み例:全国で進む導入
現場ではすでに複数の取り組みが始まっています。
■福岡県の農家では、2024年から再生二期作に取り組み、通常の1回収穫に比べて約1.4倍の収穫量を得たとの報道があります。温暖な気候と「にじのきらめき」という品種の特性を活かし、追肥や農薬管理にも工夫を凝らすことで、多収と低コストの両立に成功した事例です。
■静岡県浜松市でも、通常の1.5倍以上の収量を達成した農家があり、2回目の収穫米も「味に遜色ない」と農家自身が語っていたことが報じられました。
■茨城県・島根県など東日本地域でも実証試験が始まっており、農研機構による研究では10アールあたり950kgという収量の例も報告されています。
■ しかし「万能策」ではない・・・課題にも目を向ける必要
再生二期作をめぐっては、課題や懸念も明らかになってきています。
■土壌の地力低下
土壌の地力低下とは、再生二期作を繰り返すことで土の中の養分が減り、作物の育ちが悪くなる状態を指します。ひとつの田んぼで二度の収穫を行うと、通常よりも多くの栄養分が吸収されるため、土壌が疲弊しやすくなり、次の作付けに悪影響を及ぼすおそれがあります。適切な肥料管理や休耕期間の確保がなければ、収量や品質の低下につながるリスクが高まります。
■農機の対応
再生二期作は、一度収穫した稲の株から再び穂を出させ、二度目の収穫を行う栽培方法です。この収穫作業では、最初の刈取り時に稲を高めに刈る「高刈り」と、再生した二番穂を的確に収穫する技術が求められます。一般的に使用されている自脱型コンバインではこうした作業への対応が難しい場合があり、作物の高さに応じて刈取り部を調整できる汎用コンバインの導入が必要になるケースもあります。
■収量と品質のばらつき
二番穂は一番穂に比べて収量が2割以下になる例もあり、品質や味の劣化が懸念されています。加工米や飼料用としての活用は可能ですが、ブランド米としての流通には適さないという指摘もあります。一方で、「品質や味に遜色はない」とする声もあり、評価は分かれています。ただし、こうした品質のばらつきは価格に直結するため、消費者にとっても見過ごせない重要な要素です。
■病害虫リスク
再生二期作では、イネカメムシ、アブラムシ、イナゴといった害虫や、べと病、疫病などの病気が発生しやすくなる傾向があります。中でも被害が顕著なのがイネカメムシで、イネの穂から養分を吸汁することで斑点米や不稔米を発生させ、品質の低下や減収を引き起こします。特に出穂期から登熟期にかけての加害が深刻で、収穫量への影響も見逃せません。近年では温暖化や栽培方法の変化を背景に発生件数が増加しており、たとえば埼玉県では越冬個体数が前年比の43倍に達したという報告もあります。農林水産省も、全国的な発生拡大の可能性に対して注意を呼びかけています。
このように、再生二期作は「手軽な増産策」というよりも、地域の気候や土壌、設備環境、市場のニーズに応じて慎重に導入を判断すべき技術であるといえるでしょう。

■ 政策と現場の橋渡しを
再生二期作の可能性を最大限に引き出すには、政策的な支援が欠かせません。現場では以下のような要望が上がっています。
■高刈り対応の汎用コンバインなど、専用農機の導入支援
再生二期作を広く普及させるためには、高刈りに対応した汎用コンバインなど、専用農機の導入支援が不可欠です。汎用コンバインは、刈取部を交換することで麦・大豆・蕎麦・菜種など多様な作物に対応できる反面、通常の水稲専用コンバインに比べて価格が高くなる傾向があります。再生二期作では、1回目の刈取りは地面から約40cmの高さが推奨され、2回目はさらに低い位置での刈取りが求められるため、従来型の機種では対応が難しいという課題があります。こうした事情を踏まえると、再生二期作を次世代農業の新たなモデルとして位置づけるためにも、政府による早急かつ実効的な支援が求められます。
■土壌改良や施肥・病害虫対策に関する技術支援の拡充
土壌改良や施肥・病害虫対策に関する技術支援の拡充とは、再生二期作に適した土づくりや、栄養管理、害虫の発生を抑えるための知識や技術を行政や研究機関が農家に提供する取り組みです。専門的な指導が行き届くことで、品質や収量の安定が期待されます。
■再生二期作による米の販路確保への後押し
再生二期作による米の販路確保への後押しは、二番穂で収穫した米を確実に販売できるよう、流通先の確保や加工用米としての需要開拓を行政や関係団体が支援することを指します。販路が明確になることで、農家が安心して再生二期作に取り組めるようになります。
単なる増産ではなく、持続可能な農業を目指すには環境整備が不可欠です。農家の努力だけに依存するのではなく、政策としての支援が「広く薄く」ではなく「狭く深く」届くことが求められています。
■ 気候変動の時代、「変化に対応する農業」をどう支えるか
再生二期作は、温暖化という本来であればネガティブに受け取られがちな変化を、あえて「活かす」方向で生まれた技術です。これまでの常識にとらわれず、新しい栽培方法に挑戦する動きそのものが、すでに農業界にとって大きな一歩といえるでしょう。
ただし、それが本当に農家にとって“希望の光”であり続けるためには、現場での検証と改善、情報共有が不可欠です。導入の可否を一律に判断するのではなく、地域性・設備・人材など複合的な視点で冷静に見極めることが求められます。
私たちのような農業機械の提供に関わる企業も、現場の変化に伴走する存在として、課題解決に向けた支援を続けてまいります。
再生二期作は、決して魔法のような「打ち出の小づち」ではありません。しかし、地に足のついた「挑戦」として未来の農業を形づくる一つの道になる可能性を秘めています。希望と冷静な視点の両立こそが、これからの農業を支えるカギになるのではないでしょうか。
こちらの記事も併せてお読みください!
■ 参考出典一覧 参考出典:一部記事を要約・引用
- FBS福岡放送(2025年7月24日)
「【コメ】収穫が1.4倍「再生二期作」取り組む農家は「国は農家守る努力を」アメリカ産米の輸入割合を拡大へ」 - NHK秋田 NEWS WEB「日米協議 石破首相合意 県内のコメ農家などの反応は」(2025年7月23日)
- Yahoo!ニュース 静岡朝日テレビ(2025年5月20日)
「コメ不足のいまだからこそ重宝?『再生二期作』とは」 - 日刊ゲンダイDIGITAL(2025年7月18日)
「コメ増産の切り札として注目「再生二期作」の理想と現実…土地がやせ細るネガティブ要素も」 - 日本農業新聞 特集(2025年7月15日)
「[特集]注目・水稲の再生二期作 各地の実践例や課題は」