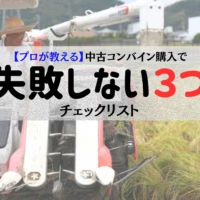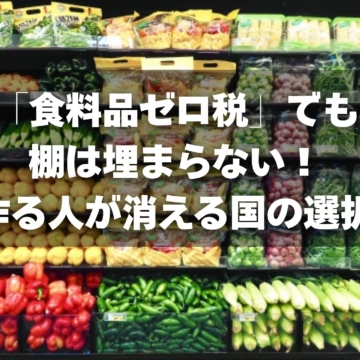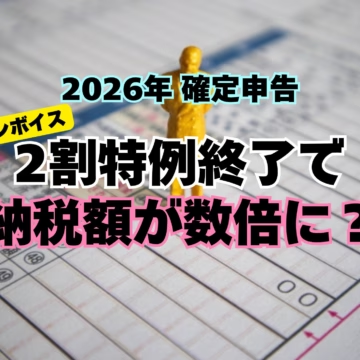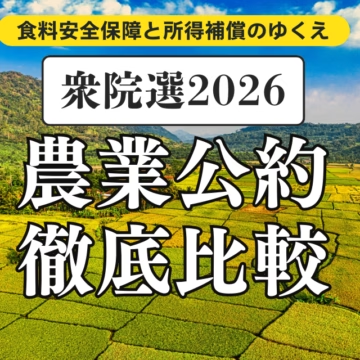稲の再生二期作・高収を叶える7条件|科学的データに基づく農業成功術【2025年最新版】
前回の記事「再生二期作のデメリットとは?」に続き、今回は「具体的な実践方法を知りたい」「実際にどうやって始めればいいのか」という読者の皆様の声にお応えします。農林水産省や農研機構の研究データ、各地の普及センターが公開している技術資料に基づき、再生二期作を成功させるための具体的なポイントを整理してご紹介します。
再生二期作は確かに注目の技術ですが、科学的根拠に基づいた適切な技術で取り組まなければ期待した結果は得られません。研究機関や試験場のデータから見えてきた「成功の7つの条件」を詳しく解説いたします。
【基礎知識編】再生二期作の科学的メカニズム
再生二期作とは、一番穂収穫後に残った稲株から発生する「ひこばえ(二番穂)」を利用して二度目の収穫を行う栽培技術です。農研機構の研究によると、この技術の成功には稲の「再生能力」という生理学的特性が重要な役割を果たします。
稲の再生能力は品種によって大きく異なり、また気温や日照条件、栄養状態に大きく左右されることが明らかになっています。特に、一番穂収穫後から二番穂の出穂までに必要な積算温度は約800-1000℃とされており、この条件を満たす地域でなければ十分な収量は期待できません。
再生二期作成功の7つの条件
条件1:気象条件の適合性
農林水産省の技術指針によると、再生二期作に適した気象条件は以下の通りです。
必要な気温条件
・一番穂収穫時期(8月下旬-9月上旬)の平均気温:25℃以上
・二番穂生育期間中(9-10月)の平均気温:20℃以上
・霜害回避のため、初霜日が11月中旬以降
日照条件
・9-10月の日照時間:月間150時間以上
・曇天が続く地域では収量・品質の低下リスクが高い
これらの条件から、九州地方や四国地方、本州では関東以西の平野部が適地とされています。農研機構の全国調査では、北海道や東北地方の多くの地域では気温不足により安定した収量確保が困難とされています。
条件2:品種特性の理解と選択
農研機構の品種特性試験データによると、再生二期作に適した品種には明確な特徴があります。
再生能力の高い品種
・にじのきらめき:九州で開発された再生専用品種
・ひとめぼれ:中生品種で再生力が安定
・あきたこまち:病害虫抵抗性も高い
品種選択の科学的根拠
各都道府県の農業試験場データでは、「にじのきらめき」が最も安定した再生能力を示し、一番穂に対する二番穂の収量比率は平均35-45%となっています。一方、「コシヒカリ」は市場価値は高いものの、再生能力にばらつきがあり、技術的な難易度が高いことが報告されています。
条件3:適切な刈取り技術
農林水産省の技術マニュアルでは、刈取り高さが再生二期作の成否を決定する最重要因子としています。
推奨刈取り高さ
・地上部から35-45cm(稲株の下位2-3節を残す)
・刈取り面は水平に、茎を潰さないよう注意
科学的根拠
農研機構の試験では、刈取り高さ15cmでは二番穂発生率が20%以下に留まるのに対し、40cm高刈りでは80%以上の発生率を確認しています。これは、下位節に蓄積された養分と生長点の保護が再生に不可欠なためです。
条件4:栄養管理の最適化
二番穂の生育には、一番穂とは異なる施肥体系が必要です。各県普及センターの指導指針を総合すると
基本的な施肥プログラム
・一番穂収穫直後:速効性窒素で10a当たり2-3kg
・収穫後7-10日:リン酸・カリ主体の化成肥料
・出穂前15-20日:穂肥として窒素1-2kg
栄養管理の科学的根拠
農研機構の研究では、一番穂収穫後の土壌中養分は大幅に減少しており、特に窒素成分の速やかな補給が二番穂の茎数確保に直結することが確認されています。
条件5:水管理技術の確立
再生二期作における水管理は、従来の水稲栽培とは異なるアプローチが必要です

基本的な水管理
・収穫直後:浅水管理(2-3cm)で根の活力維持
・再生初期:間断灌漑で新根の発生促進
・出穂期以降:浅水維持で登熟促進
水管理の科学的根拠
各県農業試験場の研究では、適切な水管理により根圏の酸素供給を改善することで、株の再生能力が30%以上向上することが報告されています。
条件6:病害虫防除の強化
再生二期作では、一般的な水稲栽培以上に病害虫対策が重要となります。
主要な害虫対策
・イネカメムシ:出穂期前後2回の薬剤散布
・ツマグロヨコバイ:ウイルス病媒介防止のため重点防除
・イナゴ類:二番穂期に発生量が増加
防除の科学的根拠
農林水産省の病害虫発生予察データでは、二番穂期(9-10月)にイネカメムシの発生量が一番穂期の1.5-2倍に増加することが確認されており、この時期の防除が品質確保の鍵となります。
条件7:収穫・調製技術の最適化
二番穂の収穫は、一番穂以上に適期判定が重要です。
収穫適期の判定
・出穂後40-45日(一番穂より短い)
・籾水分20-25%
・黄化率80%以上
品質保持技術:
・乾燥温度:45℃以下(一番穂より5℃低く)
・通風時間:十分な時間をかけた緩慢乾燥
・貯蔵水分:15%以下で害虫発生防止
【技術分析編】導入時の検討事項
必要な機械・設備
再生二期作には専用の機械設備が必要な場合があります。
高刈り対応機械
・汎用コンバイン:刈取り高さ調整機能必須
・既存機械の改造:メーカーによる改造サービス利用
費用対効果の検討
各地域の農機具メーカー資料によると、高刈り対応への機械改造費は50-100万円程度、新規導入では200-400万円程度の投資が必要とされています。
経済性の評価
農林水産省の経営分析資料に基づく収益性の試算
収量面での効果
・全国平均:一番穂530kg/10a + 二番穂180kg/10a = 合計710kg/10a
・従来比:約134%の収量向上
コスト増加要因:
・追加肥料費:10a当たり8,000-12,000円
・追加防除費:10a当たり5,000-8,000円
・追加労働時間:10a当たり5-8時間
【地域適応編】各地の取り組み状況
九州地方での展開
農林水産省九州農政局の報告によると、福岡県、熊本県、鹿児島県で試験的導入が進んでいます。特に福岡県では県独自の技術指針を策定し、普及センターを通じた技術指導体制を整備しています。
関東地方での可能性
関東農政局管内では、茨城県、栃木県で実証試験が実施されており、平野部では一定の成果が確認されています。ただし、山間部では気温不足により安定した収量確保が困難な地域もあります。
今後の研究課題
農研機構では以下の研究を継続中です。
・気候変動に対応した品種開発
・省力化技術の確立
・土壌肥沃度への長期的影響評価
まとめ:科学的根拠に基づく判断を
再生二期作は、適切な条件下で実施すれば確実に収量向上が期待できる技術です。しかし、その成功には科学的な根拠に基づいた技術の習得と、地域の気象・土壌条件への適応が不可欠です。
導入前のチェックポイント
□ 地域の気象条件が適合している
□ 適品種を選択できる
□ 高刈り対応の機械がある(導入可能)
□ 追加の労力・コストを許容できる
□ 販売先の確保ができている
導入を検討される際は、最寄りの普及センターや農業改良普及員にご相談いただき、地域の実証データを参考に慎重に判断されることをお勧めします。
再生二期作は、気候変動時代における農業技術の一つの答えとして、今後も研究・改良が続けられる重要な技術です。科学的根拠に基づいた適切な技術で取り組むことにより、持続可能な農業経営の一助となることを期待しています。
参考文献・出典
- 農林水産省「水稲の再生二期作に関する技術指針」(2024年改訂版)
- 農研機構「再生二期作の品種特性と栽培技術に関する研究報告」(2023-2024年)
- FBS福岡放送「【コメ】収穫が1.4倍「再生二期作」取り組む農家は「国は農家守る努力を」アメリカ産米の輸入割合を拡大へ」(2025年7月24日)https://news.ntv.co.jp/n/fbs/category/economy/fs761a8b9a5fe0456f9391d02a31d20ef5
- 静岡朝日テレビ「コメ不足のいまだからこそ重宝?『再生二期作』とは」Yahoo!ニュース(2025年5月20日)https://news.yahoo.co.jp/articles/bed92cb899895995a196c268d598dd892a78b0ee
- 日本農業新聞「[特集]注目・水稲の再生二期作 各地の実践例や課題は」(2025年7月15日)https://www.agrinews.co.jp/specialissue/index/288698
- 各都道府県農業試験場「再生二期作実証試験報告書」(2023-2024年度)
- 農林水産省病害虫防除所「令和6年度病害虫発生予察特殊報」
- 九州農政局「九州地域における再生二期作の展開可能性調査報告」(2024年)
関東農政局「関東地域水稲再生二期作実証事業報告書」(2024年)


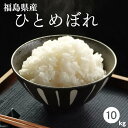

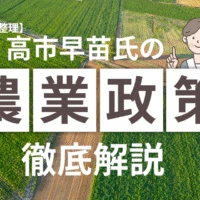


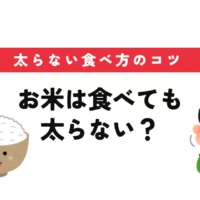

-200x200.avif)